横幹連合ニュースレター
No.014, July. 2008
<<目次>>
■巻頭メッセージ■
追い風を はらむ帆を
木村 英紀 横幹連合会長
理化学研究所
■活動紹介■
【参加レポート】
●2008年度定時総会
■参加学会の横顔■
●日本リアルオプション学会
■イベント紹介■
●第2回横幹連合シンポジウム
●これまでのイベント開催記録
■ご意見・ご感想■
ニュースレター編集室
E-mail:
* * *
横幹連合ニュースレター
No.014 July 2008
◆活動紹介
●
【参加レポート】
2008年度定時総会
特別講演「横断型基幹科学技術」講師:吉川弘之氏(5月14日)
* * * * * * * * *
2008年度定時総会 特別講演「横断型基幹科学技術」
講師:吉川弘之氏
日時:2008年5月14日
会場:学士会分館(東京・本郷)
【参加レポート】
松浦 執氏(東海大学開発工学部 准教授、形の科学会)
2008年5 月14日、2008年度総会に先立ち、横幹連合会長の吉川弘之氏により「横幹連合活動の成果と今後の展開」と題した講演が行われた。横幹連合においては、基礎理論の構築そのものが一つのミッションとなっている。ではなぜ、基礎理論の構築が必要なのか。筆者は、吉川氏の講演から、次のような感想を得ることができた。異質な分野の研究者が議論を共有して、新しい discipline(学問領域)を創造したり、既存の領域の見直しを図ろうとするときには、共通の目的と、共有できる基礎理論が必要である。その理論が、「行動」(注1)に根拠を与える。
現代の科学技術文明において、我々は、拡大する「現代の邪悪なるもの」(貧困や病気、戦争、地球環境の悪化や生物種の絶滅など)の只中にいるようである。開発学のこれまで蓄積された知識は、意識して人類が生き延びるための知識に展開し構築して行くことが、我々に要請されている。横幹連合は、その本質として既存の disciplineの存続よりも、来るべき知と人類の営為を創出するために存在するのではないだろうか。
以下、吉川弘之氏の講演内容について、その要旨を報告する。
今日(「悪夢の時代」)の、研究者にとってのNightmare Research(社会のニーズに応え得る知の成果が基本要素技術にならないで停滞する状態)は、どのようにすれば乗り越えられるのだろう。
伝統的な土着知識では、事実知識と使用知識とが組み合わされて、その社会にとって意味(事実+使用=意味)のある経験的な知識が形成されていた。そこでは、ローカルな固有性が役立つものとされた。しかし、18世紀から20世紀にかけて、存在の科学は「自然科学」、使用の科学は「設計科学」、意味の科学は「社会科学」として、それぞれ個別に体系化が進んできた。科学的知識には普遍性が重視され、事実知識の比重ばかりが高くなった。さらに、事実知識は社会的な意味から切り離されてしまい、地球環境も制御や保全の対象とはまだ考えられていなかった。これまでの人工物観は、開発型の豊かさを追求するものであったのだ。
しかし、産業活動が地球環境にさまざまな影響を及ぼしていることが明らかになり、21世紀には、社会的持続性に配慮した行動が必要とされている。中世に、生存のための科学が要請されていた状況とそれは類似して、「人工物観における歴史的回帰」といった状況が生じているのだ。生存と持続のための科学における圧倒的な知識不足が、痛感されている。
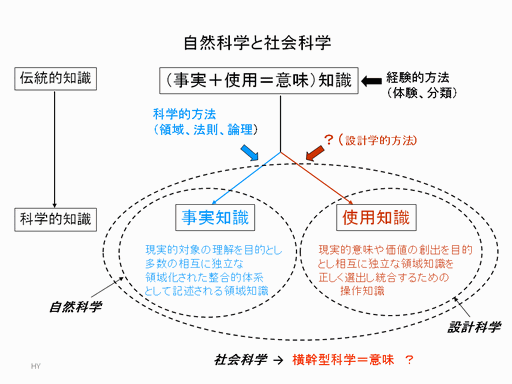 |
したがって、横幹科学とは「意味の復権」を通しての学問の先祖帰り(回帰)でもあるのだ。事実知識と使用知識、更に意味知識を合わせた「三つ組みの科学」を統合しなければならない。
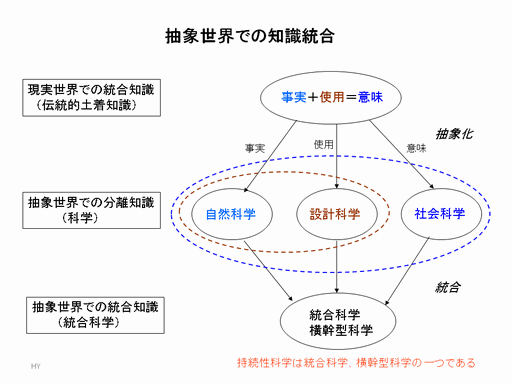 |
必要な知識と行動は多岐にわたる。人工物の総体の機能を対象とするために、これまでの disciplineだけでは対応ができない。持続可能な社会に向けた産業の重心移動(産業変革)が必要になるのである。
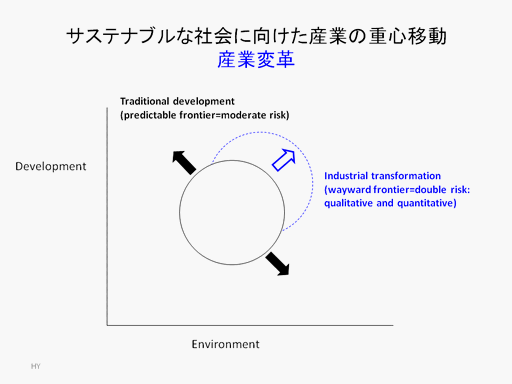 |
ところで、なぜ synthesis(統合)の工学、つまり使用の科学(「設計工学」)は、これまで充分な発達を遂げることができなかったのだろう。「設計工学」は、多様な knowledge(知)を組み合わせる極めて難しい作業であり、それをまとめる基本理論がなく、拡散しやすく、評価もしにくい。
収集された個々の動植物などを分類する(カール・リンネなどで有名な)taxonomy(分類学)が、物理学などの「科学」が分化したのと同じ時代に成立している。これは科学とは異なる道筋だったが、分類学も科学も、対象をひとつの視点で見る analysis(分析)を手法とすることによって、比較的容易に成果を上げることができた。このtaxonomyとは逆の統合の過程が、実際に人工物を設計する design(設計)であった。
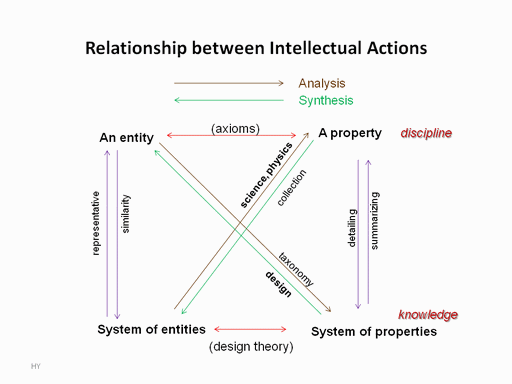 |
物理学などの「科学」は、対象としての entities(実体、データ)の systemが、どういうカテゴリーに属するか仮説を立て、そこから analysis(分析)によって法則を抽出してproperty(知の領域)を確立してきた。この過程で実体間の様々な情報は捨てられ、disciplineの分化が生み出された。
なお、この「科学」と逆の過程は、collection(収集)である。ある抽象化された領域(例えば「印象派の絵画」)という立場から、個別の実体(複数の絵画など)を収集することが、これに当たる。
ニュートンなどの理学によって成果を得た disciplinary(領域創造的)な構成を、工学が表面的に借りたために、専門分野の細分化がもたらされた。これは一面では、工学を体系化させ深化させることに寄与したのだが、工学の本質(「行動」に原理を与えること)とはかけ離れてしまう原因となった。
このような思考構造は、研究活動や学会に関わる人間の行動原理を変えてしまい、各分野の特定の視点だけで他の分野と independent(無関係)に行動する習慣ができてしまった。こうした習慣のもとでは、人工物間の関係への配慮がなくなる。そして、環境の破壊や資源の枯渇、気象変動などの社会の持続性に立ちふさがる問題への行動規範が見当たらない状況を生じさせてしまった。
研究活動が、単一の disciplineの中だけで行われることは Dream Research(夢の研究)であるので、生産性も高い。しかし、現実の行動のためには単一の disciplineだけでは不十分なことが多い。あらゆる disciplineを考慮することは大変に困難なことであるし、またアカデミックな研究としては評価され難くなるという問題も同時に存在している。しかしながら、このような「事実知識」の偏重だけでは、持続可能な社会に向けた産業の重心移動(産業変革)は実現できないのだ。
産総研から発刊された新しい学術雑誌『Synthesiology(構成学)』では、「研究成果の社会還元を実現するために、要素的技術をいかに統合して構成するか」「構成的・総合的な研究活動の成果を蓄積することによってその論理や共通原理を見いだす」という新しい学問の構築が目指されている。行動における synthesis(統合)が、扱われているのだ。
この試みに対して、抽象世界においても統合的知識が求められており、ここに横幹型科学への要請がある。『Synthesiology』と共に、横幹型科学の学術雑誌『横幹』は、今後さらに重要さを増すことが予想される。
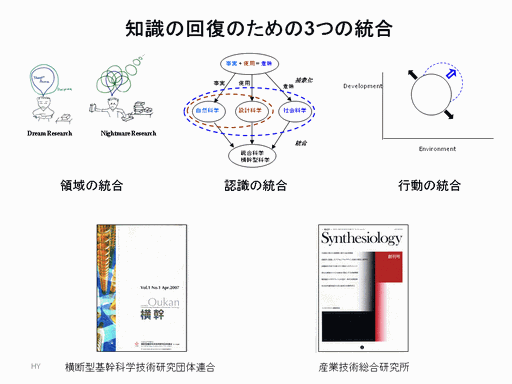 |
講演後の質疑応答では、次のような議論が行われた。
「産総研の『Synthesiology』誌は、行動の統合を論じるということだが、どのような基準で論文を採択するのか。また統合の方向性の価値判断は、どのようにして行うのか」という質問があった。これに対し吉川氏は、同誌では「結果として成功したか失敗したかに因らず、どのような行動が統合されたか」を論理的に明らかにし、「どのように、成功や失敗を導いたのかを明らかにする」ことが掲載の判断基準だと述べた。通常の論文では、成果を得た研究について議論されるが、研究過程を論理的に見直す事はあまりなされない。また、「論理」と「役に立つ」という二つの価値があるが、ここでは役に立つかどうかでは論文を判断しない、とも述べた。
木村英紀副会長からは、はじめ自然科学と技術は夫々が独立して発生し、発達したが、仏国のEcole Polytechnique(理工科大学校。最高学府の一つ)などの初期の工学教育で、自然科学が学問のモデルとして取り入れられたことや、大量生産技術において「事実知識」の要請が高まったことが、工学での行動の規範として、自然科学(細分化された学問)が導入された経緯ではなかったか、とのコメントがなされた。加えて、工学の発達につれて、制御工学などの領域横断性の高い分野が発生したが、これは従来の自然科学をある意味で超えており、横幹科学の前身ではなかったか、との指摘も木村氏からなされた。
筑波大学の山中敏正氏(感性認知脳科学専攻)からは、我々が本当に必要としている価値は、「人がどう感じるか」「社会と繋がったときどうなるか」に求められるのではないか、というコメントがなされた。
続く総会において、吉川氏は横幹連合の名誉会長として推薦され、了承された。今回の吉川氏の講演は、横幹連合と横幹科学の道程を、抽象概念において明瞭に力強く指し示す記念碑だったと言えるのではないだろうか。
注1)行動:吉川氏は知の成果を社会に活かすために行われる個人、企業、社会レベルなどの種々の活動を、広く「行動」と表現している。従って、研究や開発だけでなく、予防医療、食糧貧困の追放、生物多様性の保護、平和とガバナンスの形成なども「行動」と見なす。例えば、開発を進めるという行動と環境を保全するという行動は、学問領域の細分化によりお互いが独立して発展してきた歴史的経緯がある。その結果、伝統的な経済成長において、開発を進めて環境を破壊するか、環境を保護する代わりに産業発展を抑制するか、お互いのトレードオフの関係が生じた。しかし、二つの行動を統合してトレードオフの関係を解消することができれば、社会的持続性に配慮した産業の重心移動に結びつく、新たな知の成果が得られることになるはずだ。
(注釈文責:編集室)
| ▲このページのトップへ |
