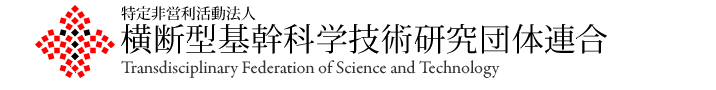第16回横幹連合コンファレンス開催のお知らせ
第16回横幹連合コンファレンスは,大会テーマを「学際融合による復興と共創」とし,2025年12月13日(土),14日(日)に金沢工業学・扇が丘キャンパス(石川県野々市市)で開催いたします.
横幹連合コンファレンスは,学術の枠を超えた知の融合を促し,新たな社会的価値を創造するための貴重な場です.自然科学,人文・社会科学,理工学,情報科学など多様な分野の専門家が一堂に会し,未来社会の構築に向けた学際融合研究の最新成果が発表されています.また,現在の社会課題や技術的な挑戦に向き合い,多分野連携のあるべき姿やその方向性,達成すべき目標,そして学際的な研究を推進できる人材像についても議論されています.
さて,2024年1月1日に発生した能登半島地震は,地域社会に甚大な影響を及ぼしました.「地域ブランドを高める創造的復興」を目標に,多くの人々の協力と温かい支援のもと,復旧・復興活動が続けられています.同時に,新たな復興ビジネスモデルの創出,災害に強いインフラ技術の開発,安全で安心な街づくりの推進など,学際的研究による新たな施策の提案も求められています.そこで,特別講演およびプレナリー講演では、能登地方の災害復旧の現状や復興の課題について,第一線で活躍される有識者の方々に話題提供や問題提起をしていただく予定です.将来起こりうる災害への備えとして,多様な学術分野が連携し,どのような対策を講じるべきかを考える契機となることを願っています.
12月の金沢は、凛とした冬の空気に包まれながら,歴史・文化,そして日本海の美食を楽しめる特別な季節です.学際的ネットワークを広げる絶好の機会となる本コンファレンスへ,ぜひお仲間と共にご参加ください.オーガナイズドセッションのご提案,一般セッションおよびポスターセッションへのご投稿を心よりお待ちしております.

実行委員長
鈴木亮一(金沢工業大学) |

プログラム委員長
河合宏之(金沢工業大学) |
主 催:特定非営利活動法人横断型基幹科学技術研究団体連合
横幹連合35会員学会
応用統計学会,形の科学会,経営情報学会,計測自動制御学会,研究・イノベーション学会,行動経済学会,国際戦略経営研究学会,システム制御情報学会,社会情報学会,商品開発・管理学会,スケジューリング学会,日本生物工学会,日本イノベーション融合学会,日本MOT学会,日本応用数理学会,日本オペレーションズ・リサーチ学会,日本開発工学会,日本感性工学会,日本経営工学会,日本経営システム学会,日本計算機統計学会,日本システム・ダイナミクス学会,日本シミュレーション&ゲーミング学会,日本情報経営学会,日本信頼性学会,日本知能情報ファジィ学会,日本デザイン学会,日本統計学会,日本バーチャルリアリティ学会,日本バイオフィードバック学会,日本品質管理学会,日本リアルオプション学会,日本リモートセンシング学会,日本ロボット学会,品質工学会
共 催:金沢工業大学
後 援:一般社団法人システムイノベーションセンター
2025年度の木村賞のファイナリストが決定いたしました。
詳しくはこちらをご覧ください。
<特別講演>
演題:「文理融合による社会実装教育研究の実践」
講師︓⾦沢⼯業大学 副学⻑ 電気・光・エネルギー応⽤研究センター所⻑ ⼭⼝ 敦史 ⽒
概要:「入学してから卒業するまでの間に学生をどれだけ成長させるか」という教育付加価値で日本一を目指す金沢工業大学における教育システムについて紹介する。特に、文理融合の学科も新設した中での社会実装教育研究について紹介する。
略歴:1986年東京大学理学部物理学科卒。同大学大学院理学系研究科(物理学専攻)博士課程修了。1991~1993年、ERATO榊量子波プロジェクト研究員。1993年、NECに入社。同社基礎研究所主任を経て、2001~2003年、光・無線デバイス研究所主任研究員(青色LDチームリーダー)。2003年、NECを退社し、稲盛財団学術部部長、ERATO上田マクロ量子制御プロジェクト技術参事を経て、2006年本金沢工業大学工学部教授就任。2024年より同大副学長。
|
 |
<プレナリー講演>
演題:「インフラ老朽化対策と災害復旧に向けた学際融合」
講師︓ ⾦沢⼯業⼤学 学⻑補佐 地域防災環境科学研究所所⻑ 宮⾥ ⼼⼀ ⽒
概要:昨年、能登半島では、市民生活に欠かせない社会インフラが、地震と大雨で被災した。また、全国各地で、道路の老朽化が進行している。これらの復旧や対策に、土木工学、建築学、心理学、情報工学、メディア情報などの、学際で取り組むプロジェクトについて紹介する。
略歴:東京工業大学で学位取得後、2001年に金沢工業大学に着任。土木学会では大学大学院教育小委員会や教育企画・人材育成委員会の委員長を歴任。現在は、同学会のコンクリート委員会の常任委員、JSTの創発的研究支援事業アドバイザー、SIPの研究開発責任者。
|
 |
<能登復興特別セッション>
「能登半島復興パネル討論会」
趣旨:2024年能登半島は地震と豪雨に被災し、人的・物的に大きな被害を受けた。その復興は未だ途半ばで、被災地域に物理的・経済的・情報システム的、メンタル的にどのような支援を行うべきかも明確ではない。今回は能登復興に関係し現場をよく知る官民の方々の知と行政問題・健康マネジメントの専門家の知との統合を試みることで、能登半島の復旧の現状とこれからの復興の方向性を明らかにできればと考える。なお、本パネル討論は、科学技術振興機構「行政・NPOの孤立・孤独対策現場知を支援する総合知に基づく学術体制構築(研究代表者 岡 檀)」の支援を受けている。
司会:新井崇弘(多摩大学)
開会あいさつ:椿 広計(横幹連合、情報・システム研究機構)
パネル討論:コーディネータ 西尾 隆(国際基督教大学名誉教授、いのち支える自殺対策推進センター客員研究員)
パネリスト
江口 清貴(神奈川県CIO兼CDO、防災DX官民共創協議会専務理事、AI防災協会客員研究員、防災科研客員研究員)
西垣 淳子(政策研究大学院大学特任教授、金沢工業大学客員教授、前石川県副知事)
藤沢 烈(能登官民連携復興センター長)
宮里 心一(金沢工業大学教授・地域防災環境科学研究所長)
山内 慶太(慶應義塾大学大学院健康マネジメント研究科教授)
閉会あいさつ:岡 檀(統計数理研究所)
<特別企画1>
「国際標準化とアカデミアとの連携~日本がリードした基本規格の国際標準化~」
趣旨:横幹連合は経済産業省と共に、国際標準化とアカデミアとの連携に関わるプラットフォーム形成を目指しています。このセッションでは、日本がリーダーシップをとれた横断的国際標準化活動を紹介します。横幹連合コトツクリコレクションに登録された日本発の研究成果や横幹連合木村賞受賞研究が、「新製品開発プロセス加速」に関わるISO規格になったことや、「分析・測定の精度」といった基本規格で日本が主導的にISO規格の原案作成を行ってきたことをそれらの国際標準化を推進したアカデミアから報告します。また、どうして日本がそのような分野でリーダーシップをとれたかも議論したいと考えます。
オーガナイザ:椿 広計(横幹連合)
オリエンテーション
日本発コトつくりの国際標準化―田口メソッドとQFD―
〇椿 広計(情報・システム研究機構),山本 渉(慶應義塾大学)
(JIS)メッシュ統計の国際標準化の取り組み―ISO 24108シリーズ開発のこれまでとこれから―
〇佐藤 彰洋(横浜市立大学)
日本がリードした分析・測定の精度に関する国際標準化
〇鈴木 知道(東京理科大学),尾島 善一(東京理科大学)
総合討論
<特別企画2>
「学びを深めるための高大連携を目指して」
趣旨:現在、高校と大学との連携が求められ、数多くの実践が行われている。それらは、学びを深めることを目的としているはずだが、連携することそのものが目的とはなっていないだろうか。本セッションでは、3つの高等学校で大学と連携している実践者と高校生からの報告を受け、学びを深めるための高大連携について考える機会とする。
オーガナイザ:木村 竜也(金沢工業大学)
学びを深めるための高大連携を目指して
〇木村 竜也(金沢工業大学)
東工アルテミスプロジェクト
〇菅沼 俊一(岡山県立東岡山工業高等学校)
大聖寺高校の高大連携事例と考察
〇高野 英樹(石川県立大聖寺高等学校)
高校生がデジタル技術に興味を持つための高大連携の取り組み―体験を通じたICT機器への関心醸成とデジタル人材育成を目指して―
〇榎本 龍政(金沢工業大学),澤田 隆之(金沢工業大学),西川 紀子(金沢工業大学),髙野 英樹(石川県立大聖寺高校),西 一志(石川県立大聖寺高校)
京都工学院高等学校における高大接続の在り方
〇大下 寛司(京都工学院高等学校)
自作電波望遠鏡の開口角が銀河観測に与える影響
〇平島 滉太郎(京都工学院高等学校)
質疑応答
<コトつくり至宝特別セッション>
コトつくり至宝としての「QRコード」
日時:2025年12月13日(土)18:15~19:00
演題:QRコード(2025年度選出「コトつくり至宝」)
講師:原 昌宏氏(株式会社デンソーウェーブ 主席技師)
場所:ホテル金沢5階 アプローズ(石川県金沢市堀川新町1-1)
物理環境,自然環境に左右されやすい場面での使用に耐え得るように,開発者である原昌宏氏は現場の視点からコードを発案し改良を重ねてきた。「現地現物を大事にする」ものづくり企業であるからこその視点である。またこの特許のオープンクローズ戦略は、日本発の技術を世界へ普及させた成功事例として大いに学ぶべき点である。QRコードは、シンプルで、身近で、多くの場面で使える汎用性を持ち、これまで長年変わらなかった社会システムを世界レベルで変えつつある。人々の行動スタイルを変えることは紛れもなくコトつくりであり、傑出した価値の創出と多大なる社会貢献から、QRコードは日本発の世界に通じる優れたコトつくりであるといえる。
|
2025.12.10 2025年度木村賞のファイナリストが決定しました。詳しくはこちらをご覧ください。
2025.11.13 セッションテーブルおよびプログラム暫定版を公開しました。
2025.10.15 参加登録の案内を公開しました。
2025.9.23 アクセス情報、キャンパスマップ、避難経路、宿泊に関する情報を掲載しました。
2025.9.22 講演原稿の受付を開始しました。詳しくは原稿執筆要領のページをご覧ください。
2025.9.18 特別講演とプレナリー講演の概要を掲載しました。
2025.9.11 特別講演とプレナリー講演の演題と講師のお名前を掲載しました。
2025.9.7 講演申込の受付を開始しました。
2025.9.5 企画セッションの一覧を公開しました。
2025.9.3 原稿執筆要領、一般講演募集、ポスターセッションのページを公開しました。
2025.6.1 企画セッションの募集を開始しました。
2025.5.22 このページを公開しました。
![]()