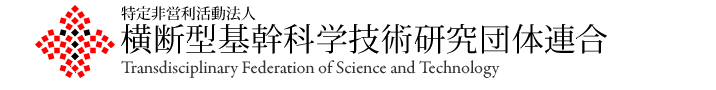開催概要
| 日時 | 2025年7月31日(木) 13:00~17:30 |
| 場所 | オークラ プレステージタワー25階会議室 (積水化学工業本社) 【アクセス】 & オンラインのハイブリッド開催 |
| 定員 | 会場 50人、 オンライン 500人 |
| 参加費 | 無料 |
| 主催 | 日本クオリティ協議会 |
| 共催 | (一社)日本品質管理学会、 (一財)日本科学技術連盟、(一財)日本規格協会 |
| 協賛 | (一社)日本能率協会、(一社) 品質工学会、 積水化学工業(株) |
| 後援 | 日本マネジメントシステム認証機関協議会、(一社)中部品質管理協会、経済産業省、(一社)日本経済団体連合会、 (公社)日本監査役協会 |
開催趣旨
AI利活用の遅れが、日本の国際的な産業競争力の低下を招くと多くの場で指摘されています。AIのメリットを十分に理解しながらも、 活用に対する懸念や不安を払拭し切れていないことや、効率化のみをゴールと考えるが故に、利活用にイノベーションを十分に起こせていないことが、大きな課題と考えられています。JAQでは、今回の「AI時代の『Qの確保』・『Qの展開』・『Qの創造』」のシンポジウムを、日本の国際競争力向上のために、AIにどう向き合っていくべきかを議論する目的で、企画致しました。「倫理」「法律」「影響を受ける社会」の3つの視点のマネジメント力で、顕在化してきたAIの安全リスクに対応することにより、安心・安全なAI運用の社会実装が可能だと考えています。今回のシンポジウムを通じて、多くの方々と商品・サービス、人、組織、経営の質(クオリティ)について議論し、AIの安全な利活用による「品質立国日本」の再生に向けて、継続的な活動につなげいくことを目指しています。
プログラム
| No | 時間 | 内容 | 講演者/出演者 (敬称略) |
| 1 | 13:00~13:15 | 開催挨拶 参加団体トップメッセージ (代読) |
飯塚 裕保 (JAQ代表幹事) |
| 2 | 13:15~13:25 | 来賓挨拶 | 今村亘 (予定) (経済産業省大臣官房審議官 [イノベーション環境局担当]) |
| 3 | 13:25~13:35 | シンポジウム開催の主旨 | 山田 秀 (日本クオリティ協議会会長、 日本品質管理学会会長) |
| 4 | 13:35~14:05 | 基調講演 「社会価値確保のための品質マネジメント」 ~人工知能時代だからこそ実現すべき経営者・専門家、 そして人々の役割~ |
椿 広計 (大学共同利用機関法人 情報・システム研究機構データサイエンス共同利用基盤施設 副施設長) |
| 5 | 14:05~14:45 | 特別講演 「科学技術 ELSIの基礎と展開 (仮題)」 |
唐沢かおり (東京大学大学院人文社会系研究科 文学部 社会心理学研究室 教授) |
| ー | 14:45~14:55 | <休憩> | ー |
| 6 | 14:55~15:15 | 企業の活用事例 1 「企業がELSIに取り組む意義~R4Dが進める人社系研究の今~(仮題)」 |
井上 真梨 (株式会社 メルカリ) |
| 7 | 15:15~15:35 | 〃 2 「サービス開発ステップに技術倫理 (ELSI視点)の導入 (仮題)」 |
廣野 元久 (株式会社リコー) |
| 8 | 15:35~15:55 | 〃 3 | 中神 徹也 (株式会社デンソー) |
| ー | 15:55~16:00 | <会場準備> | ー |
| 9 | 16:00~17:25 | パネルディスカッション ※質問は会場参加者のみ |
司会:廣野 元久 招待討論者:栗原 聡 (人工知能学会会長) 横野能将(日本監査役協会) パネリスト:山田 秀、 椿 広計、 唐沢 かおり、 井上 眞梨、 (依頼中) |
| 10 | 17:25~17:30 | 閉会挨拶 事務連絡 | |
| ー | 17:30~17:40 | <情報交換会会場に移動> | |
| 11 | 17:40~18:30 | 情報交換会 ※参加は会場参加者のみ (自由参加・無料) |
講演者/出演者/会場参加者 |
企業革新研究会(第20回)
2025.7.2
世話人:河合忠彦、平松庸一
木村裕斗、西尾弘一
次の要領で「企業革新研究会」の第20回研究会を開催致しますので是非ともご参加ください。非学会員の方の参加も可能です。
日 時: 2025年8月2日(土) 13:30~15:15 (ZOOM開催)
テーマ:「戦略的人的資源管理におけるミクロ―マクロ・リンク再考」
報告者:平松 庸一(日本大学商学部 教授)
コメンテーター:木村 裕斗(東洋大学経営学部 准教授)
野村 かすみ(労働政策研究・研修機構)
司会:西尾 弘一(中央大学経済研究所 客員研究員)
本研究会は今月より、本年2つ目のシリーズとして、戦略的人的資源管理に関する4回の研究会を開催致しております。その趣旨については下記の「SHRMシリーズの狙い」をご参照頂きたいと思います。今回はその第3回として、表記のテーマで平松先生にお話し頂きます。
参加御希望の方は学会のホームページから「7月31日までに」参加登録をしてください。登録者リストを作り、ZOOMミーティングに参加するためのURL、ID/パスワードを「前日に」BCCでお知らせします。
https://iap-jp.org/iasm/event/member/index/226
参考文献
平松庸一(2025)「ダイナミック環境下における SHRM グラデーション・モデル」国際戦略経営研究学会2025 年度春季年次大会報告要旨集,pp.65-68.
平松庸一(2023)「顧客価値経営時代の戦略的人的資源管理の新地平」日本経営品質学会編『日本経営品質学会22周年記念誌―22年の歩み―』(ISBN 978-4-9912854-6-2)pp.227-270,外為印刷.
平松庸一(2023)「不確実性の時代における経営品質-レジリエンスと対話型組織開発-」日本経営品質学会編『日本経営品質学会22周年記念誌―22年の歩み―』(ISBN 978-4-9912854-6-2)pp.271-291,外為印刷.
河合忠彦(1995)『複雑適応系リーダーシップ: 変革モデルとケース分析』有斐閣.
SHRMシリーズの狙い
本研究会では、これまで、「日本企業の“創造性/革新性の欠如”と“現場力の低下”の“並存”の原因とその克服の方策はいかなるものか」、「企業の競争力/存続能力の強化に資するIoT/AI時代のダイバーシティ・マネジメント」など を統一テーマとした研究会を開催してきました。そこから、日本企業の革新による競争力の強化、それによる日本経済の復活のためには、戦略と適合的な人的資源や組織の形成・運用が必要ではないかという共通認識が、我々の研究会では形成されつつあります。
ところが、それに直接役立ち得る理論は見当たらず、それにもっとも近そうな戦略的人的資源管理論(SHRM論)を批判的に検討したいと考えるようになりました。現在のところ、人的資源関連の研究者間におけるHRMへの戦略的接近への評価は、必ずしも芳しくないと思われます。
そこで本研究会は、そのような理論の展開の可能性を見出すべく、「戦略と適合的な人的資源や組織の形成・運用」についてのシリーズを(当面簡略化のために「SHRM論シリーズ」として)立ち上げることとしました。本年度はその第一歩として、そもそもそのような可能性があるのかということの検討を行います。4回の研究会を開催致しますので、多くの方々のご出席をお願い致します。
第27回日本感性工学会大会のご案内
日本感性工学会
1. 開催期間
2025年9月17日(水)~19日(金)
2. 会場
タワーホール船堀(〒134-0091 東京都江戸川区船堀4丁目1−1)
開催方法:対面(オンサイト)
3. 大会テーマ
違いのわかる感性
4. 大会概要
特別講演、研究発表(一般セッション、査読セッション、ポスターセッション等)、企業展示を行います。査読セッションに投稿された論文は、通常の学会論文誌の査読が行われ、査読を通ったものはそのまま学会論文誌へ掲載されます。
【大会次第】
(1)総会
2025年9月17日(水)
(2)表彰式
2025年9月17日(水)
著作賞、論文賞・技術研究賞・事例研究賞、かわいい感性デザイン賞
※総会に引き続き行われます。
(3)特別講演
特別講演 (日程調整中)
(4) その他
一般セッション、査読セッション、ポスターセッション、新企画セッション、企業展示等
第34回 企業交流会 YKK(株)のご案内
「フロントローディング実現に向けた品質工学の戦略的活用とは」
第34回企業交流会をYKK(株)において開催いたします.第34回企業交流会では「フロントローディング実現に向けた品質工学の戦略的活用とは」をメインテーマとして,製品設計前の技術開発段階での技術の創り込み,経営課題を達成するための組織的な活動について,実践例の発表と討論を行います.
主催:品質工学会 協賛:日本規格協会,日科技連,横幹連合
開催形式
現地開催 現地参加あるいはリモート配信
(後日オンデマンド配信と生成AIによるQ&Aサービスの予定)
| 日 時 | 2025年9月19日(金) 11:00~17:30 |
| プログラム | 11:00 YKKAP技術館見学 12:00 昼休憩 13:00 開会挨拶 品質工学会 会長 佐藤吉治 13:10 講演 「YKKにおける技術力強化」 YKK㈱ 池田文夫 13:50 壇上発表 (1)新規感光体駆動ユニットの技術開発における体系的MBDアプローチ ㈱リコー 松田裕道 (2)CAE活用の耐震性確保 JAXA 角有司 (3)ヒトの触覚を考慮したリール用ギヤの先行技術開発 (株)シマノ 井上徹夫 (4)TQMと品質工学の融合による開発のフロントローディング 元マツダ(株) 武重伸秀 16:00 パネルディスカッション 経営課題達成のためのフロントローディングとは(仮) 司会:畠山鎮 パネリスト:講演者,檀上発表者 17:30 閉会挨拶 理事 副会長 近岡淳 18:00~19:30 懇親会 |
| 定 員 | 会場参加先着50名 |
| 締切日 | 2025年9月5日(金)ただし定員になり次第締め切ります. |
| 参加費 | 会員9,000円 非会員は事務局へお問合せください(懇親会は別途料金8,500円予定) 当日リモート配信8,000円 (後日オンデマンド配信有り) |
| 事務局連絡先 | event_info@office.rqes.or.jp |
| 申込先 | 学会ホームページよりWEB申込み 2025年4月中旬より受付開始予定 |
SSI2025 発表募集(CFP: Call for Papers)
計測自動制御学会 システム・情報部門 学術講演会(SSI2025)は,システム・情報に関する基礎理論から工学的実システム,さらには社会経済システム,生命システムなど多様な広がりを持つシステム情報分野の研究発表を募集します.
1. 会場・会期・形式
- 会場: 東北大学青葉山キャンパス(仙台市地下鉄東西線 青葉山駅 直結)
- 会期: 2025年11月12日[水],13日[木],14日[金]
- 形式: オンサイトポスター発表(非発表者はオンラインでの参加も可能)
2. 発表募集(New!)
SSI2025では,未発表の内容だけでなく,当部門の部会主催のシンポジウムや研究会,SICE Annual Conference および他学会主催講演会などで既発表の内容も募集します.発表のカテゴリを以下の2つとします. 既存の部会・調査研究会に所属しない方の研究発表も広く募集します.
- 一般セッション(General Sessions)
システム・情報部門の部会・調査研究会(部会・調査研究会: システム工学,知能工学,自律分散システム,社会システム,コンピューテーショナル・インテリジェンス,境界と関係性を視座とする価値創発指向システム学),またはシステム・情報一般に関連する発表 - スペシャルセッション(Special Sessions)
事前に提案された特定のテーマに関連する発表
2-1.発表・参加形式
現地でのポスター発表を基本とし,審査により選ばれた発表は口頭発表となります(ご自身が発表される日時には現地で参加してください).事情により現地参加できない方のためにオンライン上での非同期型のコミュニケーションシステムを用意しています.現地参加できない場合にご活用ください.
すべての発表者は以下の2点を作成・提出していただきます.また,お申込み時には発表情報として,タイトル,著者,所属,アブストラクト(和文100〜200字,英文50〜100ワード),希望するセッション,キーワード,賞へのエントリーなどを準備していただきます.
- ポスタースライド(1枚のポスター型でも複数枚のスライドからなるものでもよい)
- 発表論文(1~6ページ)
2-2.スペシャルセッションの募集
SSI2025では,スペシャル・セッション(SS)として,特定のテーマに関してまとまった発表・ディスカッションや領域のアピールを行なっていただくことができます.SSの規模としては5件~30件程度を想定しています.なお,クローズドなSSを企画することはできません.発表者には発表申込時に,採択されたSSを含むセッション一覧の中から最もふさわしい一つを選択していただきます.
募集締切は,2025年7月11日[金]です.申し込みは[スペシャルセッション]のページよりお願いいたします.
2-3.重要日程
- スペシャルセッション募集締切: 2025年7月11日[金]
- 申込サイト開設: 2025年8月4日[金]
- 発表申込締切: 2025年8月29日[金]
- 発表論文投稿締切: 2025年9月19日[金]
- ポスタースライド提出締切: 2025年10月3日[金]