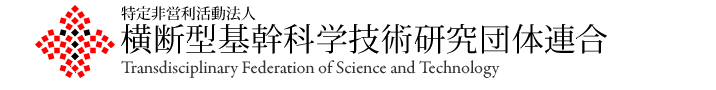日時:
2026年2月17日 @ 1:00 PM – 4:30 PM
場所:
日本学術会議講堂, 東京都港区六本木7-22-34
日本学術会議公開シンポジウム 『AI 時代における統計科学・データサイエンスの役割と挑戦 — 公平性、信頼性、解釈可能性、AI ガバナンスの観点から』 開催日時 令和8(2026)年2月17日(火)13:00 ~ 16:30 開催地 日本学術会議講堂(東京都港区六本木7-22-34)(ハイブリッド開催) 対象 どなたでもご参加いただけます。 参加費 無料 プログラム 13:00 開会挨拶 青嶋 誠(日本学術会議連携会員/筑波大学数理物質系教授) 第一部 講演 司会:佐藤 忠彦(日本学術会議連携会員/筑波大学ビジネスサイエンス系教授) 13:15 深層学習モデルの統計的推論 -選択的推論のアプローチから- 竹内 一郎(名古屋大学大学院工学研究科機械システム工学専攻機械知能学教授/国立研究開発法人理化学研究所革新知能統合研究センターデータ駆動型実験デザインチームチームディレクター) 13:45 AIにおけるバイアスと公平性 荒井 ひろみ(国立研究開発法人理化学研究所革新知能統合研究センター人工知能安全性・信頼性ユニットユニットリーダー) 14:15 初中等教育・高等教育における新たな統計教育と探究的活動 椿 広計(日本学術会議連携会員/大学共同利用機関法人情報・システム研究機構データサイエンス共同利用基盤施設副施設長) 14:45~15:00 休憩(15分) 第二部 パネルディスカッション 司会:松井 知子(日本学術会議連携会員/大学共同利用機関法人情報・システム研究機構統計数理研究所研究主幹/教授) 15:00 AIの不確実性への挑戦 -高次元小標本の統計学からのアプローチ 青嶋 誠(日本学術会議連携会員/筑波大学数理物質系教授) 15:15 医療統計学の観点から 松山 裕(東京大学大学院医学系研究科公共健康医学専攻生物統計学分野教授) 15:30 AI時代の統計科学の構築と展開 -理論・学際・社会をつなぐ 荒木 由布子(日本学術会議連携会員/東北大学大学院情報科学研究科教授) 15:45 総合討論 16:25 閉会挨拶 西郷 浩(日本学術会議連携会員/早稲田大学政治経済学術院教授) 申込⽅法 事前に下記リンク先URLあるいはポスターのQRコードより、ご登録下さい。 参加申し込みフォームへのリンク 備考 主 催:日本学術会議数理科学委員会数理統計学分科会、数学教育分科会、数学分科会、情報学委員会情報学教育分科会 共 催:特定非営利活動法人横断型基幹科学技術研究団体連合、一般社団法人統計関連学会連合、一般財団法人統計質保証推進協会 後 援:応用統計学会、一般社団法人情報処理学会、一般社団法人人工知能学会、一般社団法人日本経済学会、一般社団法人日本計算機統計学会、一般社団法人日本計量生物学会、日本行動計量学会、一般社団法人日本数学会、一般社団法人日本統計学会、一般社団法人日本品質管理学会、日本分類学会