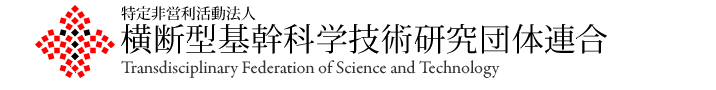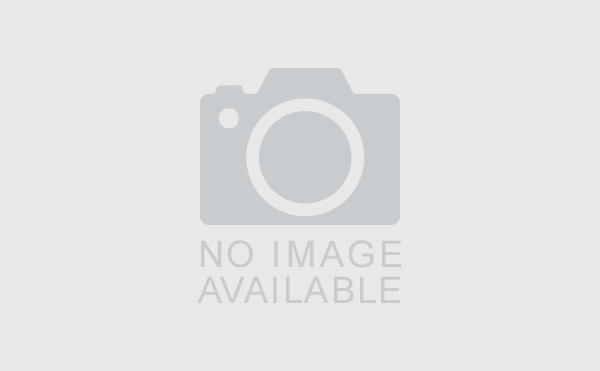第22回 企業革新研究会 2025年度 第8回
企業革新研究会(第22回)
2025.9.28
世話人:河合忠彦、平松庸一
木村裕斗、西尾弘一
次の要領で「企業革新研究会」の第22回研究会を開催致しますので是非ともご参加ください。非学会員の方の参加も可能です。
日 時: 2025年10月25日(土)13:30~15:15 (ZOOM開催)
報告者:小林英幸(SBI大学院大学 教授)
テーマ:「中国市場におけるトヨタの動向とサバイバル戦略」
コメンテーター:勝又正人(広州汽車集団 顧問)
司会:西尾弘一 (中央大学経済研究所 客員研究員)
これまでに2回開催してきました「EVウォーズシリーズ」の第3ラウンドして、今月より4回の研究会を開催致します。今回はその第1回として、表記のテーマで研究会を開催いたします。より詳しくは、下記の発表案内をご覧ください。
参加御希望の方は学会のホームページから「10月23日までに」参加登録をしてください。登録者リストを作り、ZOOMミーティングに参加するためのURL、ID/パスワードを「前日に」BCCでお知らせします。
https://iap-jp.org/iasm/event/member/index/230
発表案内
このところEV化は世界的には小休止の様相ですが、新発売車に占めるEV車の比率が40%を超える世界最大市場の中国では熾烈な競争が繰り広げられており、同市場での戦いが自動車各社のEV事業の成否、ひいては会社自体の業績を大きく左右する状況となっています。
企業革新研究会では、このような問題意識のもとに、「日本メーカーのEVウォーズ・サバイバル戦略―中国市場を中心にー」というテーマで4回にわたる研究会を開催致します。
今回は、その第1回として、小林先生にトヨタの同市場での戦略についてお話し頂きます。これまで小林先生には2回にわたってEVウォーズにおけるトヨタの戦略、ポジション等についてお話し頂いており、今回お話を伺うことにより、トヨタの戦略はどのように推移してきたのか、そのパフォーマンスはどのように評価できるか、今後の同社のパフォーマンスはどのようなものと推測されるか、等の点について多くのご示唆、ご教示が得られるものと思います。(なお、小林先生のご発表はいずれもJSMSに掲載されていますので(参考文献ご参照)、事前にそれらをご覧いただくとなお興味深く伺うことができるのではないかと思います。)
コメンテーターの勝又先生は、トヨタ自動車でチーフエンジニア等としてご活躍後、広州汽車集団(中国)の開発部門の広汽研究院で主席技官総師として製品マネジメント全般を統括され、現在は広州汽車集団の顧問をされています。先生は、SDV化における日本メーカーの遅れに早くから警鐘を鳴らしてこられましたが、今回は、小林先生のご講演について
のコメント、およびそれに関連して、中国EV市場での競争の行方、その中でのトヨタはじめ日本メーカーの巻き返しの可能性などについてお話し頂ける予定です。
参考文献
- Hideyuki Kobayashi (2022) “Evaluation of Toyota’s Strategy for BEV in Overtaking Tesla: Based on the Theories of Dynamic Managerial Capabilities and Ordinary Capabilities” JSMS Vol.14, No.1, 49-66
- Hideyuki Kobayashi (2024) “Re-evaluation of Toyota’s Strategy for BEV Based on the Theories of Dynamic Managerial Capabilities and Ordinary Capabilities” JSMS Vol.16, No.1, 35-50
- Tadahiko Kawai (2022) “Evaluation of Toyota’s Strategy for Electric Cars in Counteracting Platformers: Based on the Theories of Dynamic Managerial Capabilities and Platformers” JSMS Vol.14, No.1, 67-
- 河合忠彦(2024)『ダイナミック・マネジリアルケイパビリティの理論』(未公刊ドラフト)