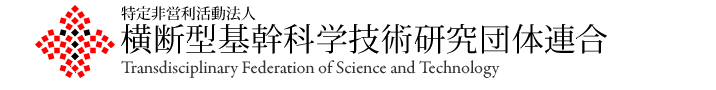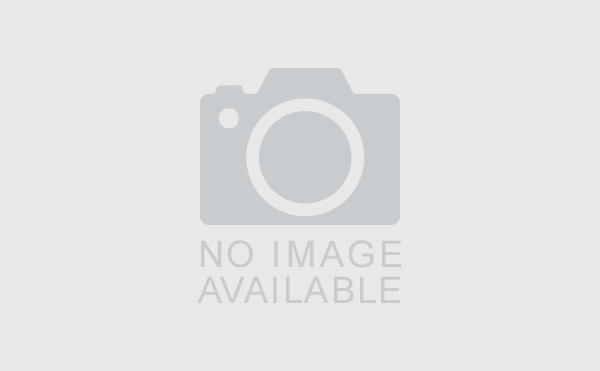No.82 Aug 2025
TOPICS
〇 第16回横幹コンファレンスは、2025年12月13日(土)、14日(日)に金沢工業大学 扇が丘キャンパス(石川県野々市(ののいち)市 扇が丘)を会場として開催されます。 HPを公開しました。詳しくはこちら。
□ J-STAGE 月間アクセスランキングはこちら
COLUMN
駅前「医療モール」(医療経営学研究の活用)による 医療イノベーションの実現、を再読する。
横幹ニュースレター編集室 武田博直(日本バーチャルリアリティ学会)小山慎哉(日本バーチャルリアリティ学会)
東京都三鷹市に、杏林大学医学部付属病院(以下、杏林大)という総合病院がある。外来患者数 約2,000人/日、入院患者数 約700人/日(2022年度)であり、隣の調布市などもカバーする救急指定病院としても有名で、三鷹市を走る市バスの5路線が「杏林大学病院前」停留所を経由するなど、地域の拠点となっている。この病院が近年、「初診外来には かかりつけ医の紹介状が必要です」と告知するようになった。
本稿では 最初に、この変化について一人の患者の目線から見てみたい。これは、杏林大に限らず、全国の大規模病院において ほぼ同じく行なわれるようになった重要な変化だからである。筆者の一人(武田、以下私)の家内は、十年前に杏林大である入院治療を受けた。その「予後検診」については、「来年の」何月何日何時にと、繰り返して予約をしてきた。すると近年、この予約の受診開始までの時間が顕著に遅れ始め、あるときは診療開始の予約時間から1時間25分も待ったという。(病院は、家からは10分の場所にある。) ちなみに、私がたまたま付き添いで同行した際にも、ある有名な診療科目の受け付けでほぼ全ての席が埋まり、その科目の人気ぶりが見て取れた。杏林大には、九州から受診に来られる患者さんもおられるそうである。このように、総合病院が希望するといわれる「プライマリケアは診療所(かかりつけ医)、二次三次医療を病院で」という役割分担を、杏林大では「かかりつけ医の紹介状」で実現しようとしている、ことが理解できた。
□ 「医療モール」
ところで、第57回横幹技術フォーラムで ご講演頂いた「医療モール」という 医療経営形態が、一般の患者にとっても関心のあるいくつかの重要な問題に、抜本的な解決方法を与えることに最近気が付いた。(なお、講演をして頂いた伊藤敦氏のご経歴については後述する。)
このフォーラムについては、横幹ニュースレターNo.64 Feb 2021に 記事を掲載させて頂いたが、ここでは 「複数の診療所が特定の空間の中に集積し、近くに 調剤薬局がある」 という形態上の特徴を述べるに留めて、「医療モール」についての話を進めさせて頂きたい。 伊藤氏が講演で「医療イノベーションの実現に向けた取り組み」として整理された、医療モールがもたらすメリットを先に再読したいためである。
- 医療モールの立地は、患者の8割が徒歩5分圏内に居住しているという。この環境においては、「プライマリケアは診療所、二次三次医療を病院で」という役割分担を、医療モールが担える可能性は高い。医療モールの展開が今より進めば、大規模病院への軽症患者の集中を避けることが期待できる。
- 医療モールは、医療法で定義された医療施設ではなく、先述の通り 複数の診療所が特定の空間に集積し、近くに調剤薬局がある開設形態である。従って、診療所の新設は「病院」の開業と異なり初期投資が大変低く抑えられる。また、複数の医師による医療ネットワークを駆使することも可能になり、実際お隣の診療所と「高額な医療機器」を共同購入・共同使用しているなどの実例もあるそうだ。一方、利用する患者においても、医療ネットワークの存在により、二次医療の患者すべてが総合病院に紹介されるのではなく、高度な治療を得意とする近隣の診療所への紹介、という別の選択肢があるかもしれない。
- 伊藤氏が医療モールに着目して悉皆調査を実施したところ、病院・診療所の総数が横這い状態であるにも係わらず、医療モールは2005年を1として2018年には8倍以上の増加が見られたなど、急激な拡大・発展があったそうだ。しかし、政府・医師会ともに、当時その増加傾向を把握していないことが分かったという。なお、医療モールには、1)総合病院の中に個人診療所が開設しているという形態、2) 大病院のすぐ近くに診療所がある形態、3) 駅ビルのテナントとして複数の診療所が開設している形態、などが見られるそうだ。
昨今、大規模病院の経営が悪化することによる 地域医療の危機についての報道が多くあり、病院の規模に応じた役割分担の必要性が より高まっているように思われる。医療モールについては もっと関心が向けられて良いし、地域医療を活性させる側面からの施策も 今後に議論を期待したいところである。というのは、技術フォーラムで指摘された以下A、Bの議論は、地域医療全体にとっての 大いに重要な問題だったからだ。しかし、これについては紙幅の事情により、改めて 別稿にて議論したい。
- 医療モールの成否は、使い勝手の良い情報ネットワーク(例えば、電子カルテの共通化)が安価に構築できるかどうかに関わるという。例えば、北海道の人口約500万人というのはフィンランドとほぼ同数なので、例えばフィンランドで行われている「患者情報の共有化」などの試みを、医療特区のような形で実施しても良いのではないか。(最後のパネルディスカッションでの、主に伊藤氏によるご発言。)
- 北海道の人口は、2040年には 現在より100万人の人口減少が見込まれているという。また、札幌市を中心に極点社会が形成され、道内の人口密度が低いことに加えて高齢化率が非常に高いそうだ。それに伴い、将来的には地方都市の公共交通の縮小や学校の廃校だけでなく、医師不足や診療科の閉鎖などから「医療インフラの維持」が困難になる可能性も、強く懸念されているという。この問題について「医療モール」という医療ネットワークを、医療経営学的な手法とすることで、地域医療の充実、強化につなげることができるのではないか。(伊藤氏講演の冒頭を、本誌文責で要約。)
□ 「医療モールと憩いのサロン」
ところで、「医療モール」の患者の出口(治療の後)について考えていたとき、この出口がもしかすると 「ソーシャルキャピタルを活用したまちづくりによる介護予防」や「憩いのサロン」の入口の一つでもある、という重大な事実に気付いた。本節では、端的にこれを解説したい。
近藤克則氏(千葉大学名誉教授)は、「住んでいるだけで、転びにくく、認知症になりにくく、糖尿病になりにくい」町があることを発見された。そして、ある町の住民を健康にできる潜在力「ソーシャル・キャピタル測定指標」(後述する)の可視化に成功されたことで、全国の「地域間健康格差の解消」、すなわち、全国を「健康で長生きできる町」にするプロジェクトの実証実験を数多く展開しておられる。繰り返すが、その場所に住むだけで「健康のまま 長生きできる町」は地元住民の協力があれば「実現が可能」なのだ。しかも、この町は上記した「測定指標」を用いて運用などの効果を明示できることから、例えば、ここでは詳しい説明をしないが「ソーシャルインパクトボンド」という行政支援では、民間人グループがある人たちを「もっと健康にします」と宣言し、工夫してそうなれば報奨金が貰える制度も用意されているという。
※ なお、本誌は No.58 Aug 2019 に「第54回横幹技術フォーラム」の中で 近藤氏をご紹介して以降、このプロジェクトに注目しており、No.78 Aug 2024 にも「”暮らすだけで健康になる” まちづくり、そこに住んでいるだけで、転びにくく、認知症になりにくく、糖尿病になりにくい、そうした町 が設計できる。講演『学際研究によるゼロ次予防の可能性』を再読する」を掲載した。後者は、平井寛 竹田徳則 近藤克則 著『まちづくりによる介護予防「武豊プロジェクト」の戦略から効果評価まで』の出版されたことが きっかけである。
近藤氏らの行なっておられることは、具体的には 近所で自由に参加できる「介護予防サロン」などの出かけやすい環境を住民の方々と一緒に整備されることである、という。ところが、 近藤氏ら「日本老年学的評価研究機構 JAGES」 の定めた「ソーシャル・キャピタル指標」の簡単な質問票で 参加者の「はい・いいえ」を集計すると、疫学的な研究から 次のようなことが分かるそうだ。このサロンに不定期に参加していれば「痴呆症のリスク」が減り「糖尿病になるリスク」も減る可能性が高い。更に 一般的にだが「未病の発症するリスク」も下がる可能性がある、という。
【参考】 愛知県武豊町 憩いのサロン
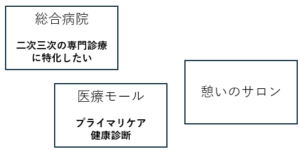
ところで、「診療モール」の患者は、いずれ退院する。このとき、もしも近くにある「憩いのサロン」を紹介されることがあれば、患者にとってこれは大変なメリットになるかもしれないことに本誌は気が付いた。以下に これを説明する。
思い出して頂きたいのだが、本誌No.64 Feb 2021に掲載した「第57回横幹技術フォーラム: 先端医療( 医用生体工学・行動神経経済学・医療経営学 )研究の現状とその活用による北海道の地域・医療イノベーション」のご紹介」では、最後のパネルディスカッションに 大きなテーマが もう一つ論じられていた。
医師による「食習慣」のメニューの改善指導である。
講演された 高橋泰城氏(当時 北海道大学脳科学研究教育センター 准教授)によれば、行動神経経済学の見地から研究すると、脳に適度な満足感を与える食習慣は、例えば「目先のごちそうに流される食生活だった人が、ダイエットに失敗しなくなる」「多重債務者で目についた商品を衝動的に購入してきた人が、その生活を断ち切ることができる」などの精神への安定効果も及ぼすという。これは、目先の(気持ちが良いという)利益が将来の不利益より高く選好されたからそうした行動になった、と考える合理的な説明がつき、論文も多数書かれているそうだ。
そこで、高橋氏は ご自身が周囲に北海道民にとって馴染みのある食材「新鮮な魚介類」「地元の野菜」を活かした、「野菜と果物の摂取量が多く、魚介・鶏肉・乳製品を主なタンパク源とする地中海式の食習慣」を薦めておられるのだという。とても評判が良いそうだ。
そして、このご講演に強く反応されたのが、「医療モール」の講演者伊藤氏だった。患者の「食習慣」を改善することに糖尿病などの再発防止効果のあることは、良く知られている。(具体的にどうするかは さておき)北海道の「かかりつけ医」が こうした「食習慣」のメニューの改善を患者さんに推奨できれば、その根拠は実証されているので、患者の健康の活性化がそのまま社会全体を健康にすることにつながるに違いない。正直、私はこのときのディスカッションの内容に大変に感銘を受けた。
しかし、「食習慣」の改善指導は、これだけで一回のテーマになる大きな課題である。
また、このときの議論も、時間の都合で 中断された。
そこで本稿では、「医療モール」という 非常に素晴らしい構想の講演の記録を再構成し、また パネルディスカッションで「食習慣」の指導という重要なテーマが議論の途中であったことに読者の注意を喚起させて頂いた。今回はここで終わり、再論をお約束したい。
「医療モール」と「憩いのサロン」が近くにある場合もあるだろう、というのは本誌独自の提案である。が、上記した「食習慣」の指導による北海道民の生活の改善と志を同じくすることは、ご理解いただけると思う。「サロンで料理講習をするかどうか」でなく、社会の健康はどうすれば実現できるかの課題解決が問題ではないだろうか。医学の発展には縦型の進歩が注目を集めるが、横断的な社会構造を考慮したアプローチの有効性を示唆する一事例と考えて、今回のテーマとさせて頂いた。
※ 以下に、「第57回横幹技術フォーラム」講師の皆さまの 当時の役職と現在を挙げる。
講演1 「脳機能計測に基づく認知症予知とオンラインコミュニケーションへの提言」
横澤宏一 ( 北海道大学大学院 保健科学研究院 教授(兼)脳科学研究教育センター 基幹教員 )
講演2 「行動神経経済学の医療イノベーションへの応用」
高橋泰城 ( 北海道大学脳科学研究教育センター 准教授。現在 北海道大学 教授 )
講演3 「医療イノベーションの実現に向けた医療モールの展開戦略」
伊藤敦 ( 北見工業大学工学部 准教授。現在 京都府立大学 教授 )
EVENT
【これから開催されるイベント】
横幹連合ホームページの「会員学会カレンダー」 をご覧ください。
また、会員学会の皆さまは、開催情報を横幹連合事務局 office@trafst.jp までお知らせ下さい。